色の3属性
色相・明度・彩度
色は、色相・明度・彩度の3つに分類できます。これらを色の3属性と呼びます。
色相(しきそう)
赤
黄
緑
青
紫
色み(色合い)の種類を表す
明度(めいど)
← 明度が低い
明度が高い →
明るさの度合いを表す
彩度(さいど)
← 彩度が低い
彩度が高い →
色みの強弱(鮮やかさ)の度合いを表す
有彩色と無彩色
色は大きく、有彩色と無彩色の2つの種類に分けられます。
有彩色(ゆうさいしょく)
色みをもつすべての色
無彩色(むさいしょく)
色みをまったくもたない「黒」「灰色」「白」のこと
色相環と色立体
色相環
虹の7色といわれる赤→橙→黄→緑→青→藍→青紫の色(スペクトルという)に、それらをつなぐ紫・赤紫を加えて、ぐるりと軸にしたものを色相環といいます。

180°反対側にある向かい合う色同士を補色といいます。
色立体
色立体とは、色の3属性を3次元にしたもので、縦軸に明度、横軸に彩度、中心の無彩色軸の周りに色相環を配しています。無彩色軸を中心に、距離があるほど彩度が高くなります。
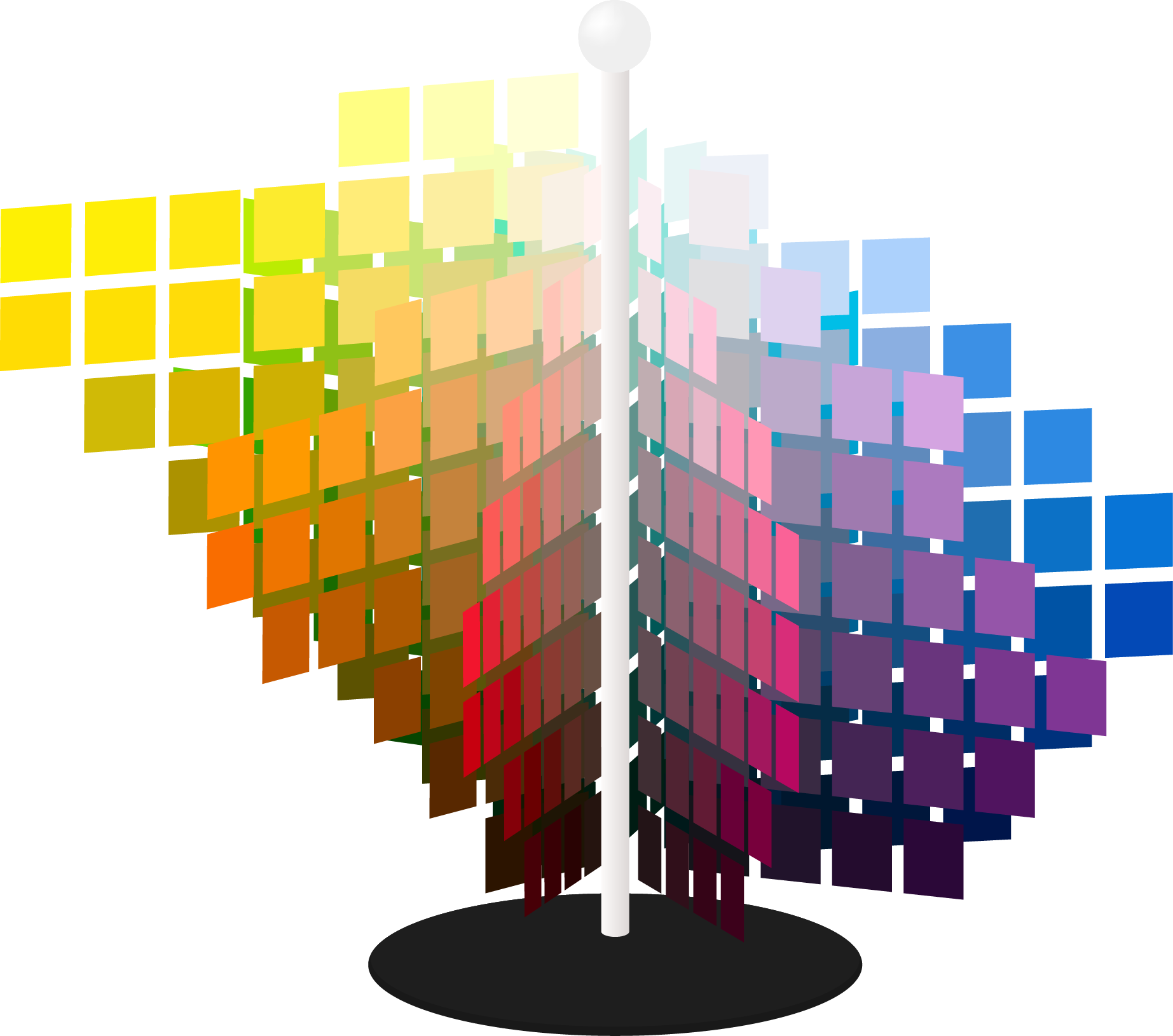
無彩色軸を通り、色立体を縦に垂直に切ると等色相面が現れます。この面上にある色はすべて色相が同じで、中心の無彩色軸を挟んだ左右の色は補色の関係といいます。
表色系
色の3属性を用いて、数値・記号で表したものを表色系といいます。
カラーオーダーシステム
色を系統的に配列した、標準となる色見本がある色彩体系のことをカラーオーダーシステムといいます。「色票」という色サンプルがあり、新配色カード199aもそのひとつです。
PCCS
PCCSとは、Practical Color Co-ordinate Systemの略で、日本名を「日本色研配色体系」といいます。一般財団法人日本色彩研究所が開発したもので、色彩調和を求めるのに適しています。
PCCSの色相環
PCCSは24色相で、各色相には色相番号と色相名が付けられています。

暖かみを感じる暖色系は、1~8の色相
温度感のない中性色系は、9~12と20~24の色相
冷たさを感じる寒色系は、13~19の色相
色相記号・色相名
- 色相記号・色相名
- 色相名(英語)
- 色相記号・色相名
- 色相名(英語)
- 1:pR紫みの赤
- purplish Red
- 13:bG青みの緑
- bluish Green
- 2:R赤
- Red
- 14:BG青緑
- Blue Green
- 3:yR黄みの赤
- yellowish Red
- 15:BG青緑
- Blue Green
- 4:rO赤みのだいだい
- reddish Orange
- 16:gB緑みの青
- greenish Blue
- 5:Oだいだい
- purplish Red
- 17:B青
- Blue
- 6:yO黄みのだいだい
- yellowish Orange
- 18:B青
- Blue
- 7:rY赤みの黄
- reddish Yellow
- 19:pB紫みの青
- purplish Blue
- 8:Y黄
- Yellow
- 20:V青紫
- Violet
- 9:gY緑みの黄
- greenish Yellow
- 21:bP青みの紫
- bluish Purple
- 10:YG黄緑
- Yellow Green
- 22:P紫
- Purple
- 11:yG黄みの緑
- yellowish Green
- 23:rP赤みの紫
- reddish Purple
- 12:G緑
- Green
- 24:RP赤紫
- Red Purple
PCCSの色相・明度・彩度
PCCSの色相:ヒュー(Hue)
PCCSの明度:ライトネス(Lightness)
PCCSの彩度:サチュレーション(Saturation)
PCCS色相環のしくみ
PCCS24色相には、心理4原色、混色の基本となる色料の3原色(黄・緑みの青・赤紫)、色光の3原色(黄みの赤・緑・紫みの青)が含まれているのが特徴です。
心理4原色:色覚の基本となる4つの色相。赤・黄・緑・青
心理補色:ある色をしばらく見つめてから目を移すと見える残像のこと
色料の3原色:減法混色の3原色
色光の3原色:加法混色の3原色
PCCSトーン
PCCSトーン
PCCSでは同じような印象やイメージを持つ明度・彩度の領域をトーンと呼び、全部で12のトーンに分類しています。

トーン:明度と彩度を合わせた概念で、色の調子
ヒュートーンシステム:色相(ヒュー)とトーンにより、色を分類したシステム
有彩色12トーン
- トーンの略記号
- トーン名
- 形容詞
- v
- ビビッド
- さえた
- s
- ストロング
- 強い
- b
- ブライト
- 明るい
- dp
- ディープ
- 濃い
- lt
- ライト
- 浅い
- sf
- ソフト
- 柔らかい
- d
- ダル
- 鈍い
- dk
- ダーク
- 暗い
- p
- ペール
- 薄い
- ltg
- ライトグレイッシュ
- 明るい灰みの
- g
- グレイッシュ
- 灰みの
- dkg
- ダークグレイッシュ
- 暗い灰みの
無彩色5トーン
- トーンの略記号
- トーン名
- 形容詞
- W
- ホワイト
- 白
- ltGy
- ライトグレイ
- 明るい灰色
- mGy
- ミディアムグレイ
- 灰色
- dkGy
- ダークグレイ
- 暗い灰色
- Bk
- ブラック
- 黒
純色・明清色・暗清色・中間色
純色(じゅんしょく):各色相の中で最も彩度の高い色=最高彩度色。(vトーン)
清色(せいしょく):純色に白もしくは黒を加えた、澄んだ色。
明清色(めいせいしょく):純色に白を加えた、明るく澄んだ色。(b、lt、pトーン)
暗清色(あんせいしょく):純色に黒を加えた、暗く澄んだ色。(dp、dk、dkgトーン)
中間色(ちゅうかんしょく):純色に灰色を加えた、くすんだ色。濁色ともいう。(s、sf、d、ltg、gトーン)
色名
慣用色名
- ■
- マゼンタ
- イタリアの地名が由来。減法混色の3原色の赤紫。
- ■
- 浅葱色
- やや緑みのある青で葱の若芽のような色
- ■
- カーマイン
- 中南米のサボテンに寄生する介殻虫のコチニールから取られた動物性染料の西洋の深紅色
- ■
- スカーレット
- ペルシャ語の織物に由来し、日本語の緋色に相当する色。
- ■
- 朱色
- 硫化水銀を原料とする鉱物顔料「銀朱」の色を表す色名。印鑑の朱肉の色。
- ■
- 萌黄
- 春に芽吹く若葉のような黄緑色。
- ■
- 群青色
- 青の集まりを意味する鉱物顔料の伝統的な色名。
- ■
- 生成り色
- 何も加工しない生地のままの繊維の色を表した色名。
- ■
- マリーゴールド
- マリーゴールドのような山吹色。
- ■
- バイオレット
- 青紫系の英色名で最も古いもののひとつ。
- ■
- モーブ
- 1856年イギリスの化学者パーキンが人類初の化学染料を発見した。その紫色の染料の色。
- ■
- ビリジアン
- フランス人ギネが特許登録した、水酸化クローム顔料をもとに作られた緑色絵の具の色名。
- ■
- セピア
- イカ墨からつくった古代の絵の具の色名。
- ■
- 茜色
- 日本最古の植物染料のひとつ。温帯アジア原生のアカネの根を原料とする。
- ■
- 瑠璃色
- 古代インド、中国で珍重された青い宝石の色を表す色名。
- ■
- コバルトブルー
- コバルトアルミン酸塩の顔料が、1777年に発見された。印象派の画家たちにこの絵の具がよく使われた。
光と色
反射・吸収・透過
「光源」「物体」「視覚」、この3つがそろって色は認知されます。
物体に当たった光は、反射するか、吸収されるか、透過するか、のいずれかの形をとります。
反射・吸収:例えばイチゴの場合、赤系統の色が反射し、それ以外の色は吸収されるため赤く見えます。
透過:ガラスは色を透過させるので、色が透けて見えます。光が通過することを、透過といいます。
屈折・干渉・回折・散乱
光の一般的なアクションとして「反射・吸収・透過」がありますが、より複雑になったものが、「屈折・干渉・回折・散乱」です。
屈折(くっせつ):光が、ガラスや水などの物質の境界を、斜めに通過するときに起こる、光の進路が変化する現象です。
干渉(かんしょう):シャボン玉の表面の色は、さまざまな色が流れるように見えます。これは、光の波の山と山が足されて振幅を大きくしたり、山と谷が合わさって振幅を小さくしたりすることで起こります。
回折(かいせつ):光には、波の性質があるので、障害物があると回り込み、波が広がって進みます。この現象を回折といい、長波長ほど回り込みは大きくなります。
散乱(さんらん):光が小さな粒子に当たってさまざまな方向に散る現象を、散乱といいます。
混色
加法混色:色光を重ねることによる混色のこと。複数の色光が眼に同時に入るので、同時加法混色ともいいます。

★原色の色(R・G・B)をすべて重ねると白(W)になる。
★補色同士を重ねると白(W)になる。

減法混色:色フィルターや色料などによる混色のこと。

★3原色の色(C・M・Y)をすべて混ぜると黒(Bk)になる。
★補色同士を重ねると黒(Bk)になる。

眼のしくみ
眼は光の情報を集める器官である。眼に入ってきた情報は、眼球の一番奥にある網膜で像を結ぶ。
網膜には、視細胞といわれる特殊な細胞がある。ここで光の情報が電気信号に変換され、視神経細胞などの細胞を経て、視神経を通じて情報は脳へ送られる。

- 強膜
- 眼球の一番外側で白目の部分。眼球を保護する役割。
- 脈絡膜
- 強膜と網膜の間にあり、眼球に栄養を送っている。
- 角膜
- 黒目の前面をおおっている。眼に入る光が最初に通過し、屈折させる。最初のレンズの役割。
- 虹彩
- 光の量を調整する。カメラの絞りのような役割で、虹彩の中央の穴(瞳孔)を広げたり狭くしたりしている。
- 水晶体
- 透明な凸レンズで、眼に入った光を屈折させて焦点を合わせる役割。毛様体の基部にある毛様体筋が、水晶体の厚みを調整している。
- 網膜
- カメラのフィルムに当たる。光を感じる細胞と、色や形を感じる細胞がある。
- 中心窩
- 黄斑の中心で、小さくくぼんでいる部分があり、最も解像度が高く、色や形がよく見える部分。
- 視神経乳頭
- 視神経が束ねられていて、眼球から脳への出発点となる。ここには視細胞がないため、像が映らない。
色彩心理
対比
明度対比:中央の色が背景の色に影響され、背景の色の明度と逆方向へ引っ張られる。

色相対比:中央の色が背景の色に影響され、背景の色の心理補色側へ引っ張られる。

彩度対比:中央の色が背景の色に影響され、背景の色の彩度と逆方向へ引っ張られる。

同化
明度同化:背景色が挿入された線の明度に近づき、白線のほうは背景色が明るく見える。

色相同化:背景色が挿入された線の色相に近づき、黄色線のほうは背景色が黄みの緑に見える。

彩度同化:背景色が挿入された線の彩度に近づき、グレイ線のほうは背景色がより彩度が低く、くすんで見える。

色彩調和
配色テクニック
アクセントカラー:単調な配色を少量の目立つ色で引き締める配色。

セパレーション:強烈すぎる配色をやわらげたり、ぼんやりした配色を引き締める配色。

グラデーション:色を段階的に規則的に変化させた多色配色。
● 色相のグラデーション

● 明度方向のグラデーション

● 明度と彩度のグラデーション

その他
色彩心理
企業のイメージを色で表現したものをコーポレートカラーという。
軽い色と思い色を使用する際には、配色の明度差や色の分量などを配慮する。
赤は活動的、青は信頼・誠実、緑は自然や優しさをアピールするのに適している。
色陰現象
グレイが、周囲を鮮やかな有彩色で囲まれたとき、その有彩色の補色の色味を帯びること。
縁辺対比
明度の異なる色を隣接して配色したとき、その境界線に明るい帯と暗い帯が見える。グレイの場合、暗いグレイに接する部分でより明るく見え、明るいグレイに接する部分でより暗く見えるようというように、対比現象のひとつである。
主観色
物理上、色みのないところに、人間の主観から何らかの色が見える現象。
ベンハムトップ(ベンハムこま)
制作者の名前にちなんでベンハムトップと呼ばれるパターン。回すことによって主観色が生じて色が見える。
加法混色の種類
併置加法混色:異なる色の、小さな点の集まりが融合して、ひとつの色に見えるような混色のこと。
継時加法混色(回転混色):いくつかの色で塗り分けられた円盤を、高速度で回転させると、ひとつの色に見えるような混色のこと。
-
前のページ
- 一覧に戻る
-
次のページ














